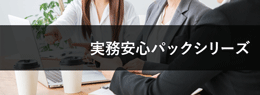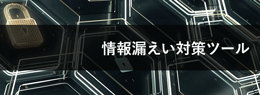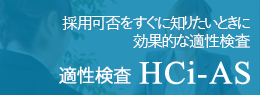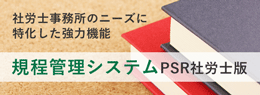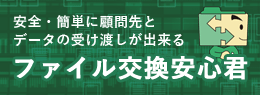2025/06/16(月) コラム
- HOME
- 特集・記事
- 弁護士佐久間先生のコラム
- 新型コロナウィルスの感染予防のためにテレワーク中のさぼり行為に対する懲戒処分
新型コロナウィルスの感染予防のためにテレワーク中のさぼり行為に対する懲戒処分
1 労働契約に基づく懲戒権の発生
テレワークを命じた従業員が、所定労働時間中に会社貸与のパソコンの前から離れて2時間以上も戻ってこないので、上司が確認をしたところ、「別の場所で新商品の企画を考えていた」と答えた場合、さぼり行為として、当該従業員を懲戒処分にすることはできるでしょうか。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立」します(労働契約法6条)。この労働契約に基づき、労働者は使用者に労務を提供する義務を負い、使用者は労働者より労務提供を受ける権利を有します。
さぼり行為は、労働契約上の労務提供義務に違反した債務不履行であるため、このことから直ちに使用者が懲戒権を行使することはできません。
ただし、労働者は、信義に従い誠実に労務提供義務を履行しなければならない(労働契約法3条4項)という職務専念義務を負っています。この義務違反を広くとらえて懲戒処分を科すことは許されませんが、職務専念義務違反の程度が著しく、他の従業員の職務執行が妨害され、職場の秩序が乱されたという場合に懲戒処分が問題になってきます。
労使関係において、使用者が制裁罰を科す権能を有するのは、労働契約にその根拠が求められます。すなわち、労働者は労働契約によって使用者の懲戒権の発生を認めるのですから、そもそも労働契約に懲戒の定めがなければ懲戒権は発生しないことになります。就業規則を作成するときは、「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」(労働基準法89条9号)について定めをしなければなりません。規定を置けば無限定の懲戒権が認められるかというと、そうではなく、その規定が合理的で、労働者に周知させていなければ、労働契約の内容にはなりません(労働契約法7条)。
就業規則に根拠規定があり、使用者に懲戒権が発生したとしても、その行使がすべて有効になるものではなく、労働契約法は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」(15条)と定めています。しかし、同法は、懲戒の事由、懲戒の種類・程度、手続などの要件と効果を明示しておらず、結局は具体的な内容を就業規則に委ねています。
そこで、人事労務担当者としては、就業規則や労働契約に懲戒の定めがあるのか、あるとしてその内容が合理的であるか、また労働者に周知しているかをまず点検してください。
2 懲戒権行使の要件
次に、使用者に懲戒権があるとしても、その懲戒権を行使するためには相当な根拠と理由が必要となります。当該従業員より「商品の企画を考えていた」との弁明がなされているのであれば、懲戒事由に該当する事実の存在につき合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の根拠と理由が具備されるときに、使用者は懲戒権を行使することができると解されます。
そして、使用者が懲戒権を行使する場合においては、事実誤認に基づく懲戒処分、懲戒事由の程度と比較して均衡を失する懲戒処分を防止するために、慎重かつ適正な手続を履行することが要求されます。
人事労務担当者としては、当該従業員から詳細な事情聴取を行い、その事実関係と動機・目的等を正確に把握し、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情」(労働契約法15条)を調査しなければなりません。前述したとおり、さぼり行為は、労働契約上の労務提供義務に違反した債務不履行であるため、懲戒権を行使するには、当該従業員の職務専念義務違反により、具体的に、他の従業員の職務執行が妨害され、職場の秩序が乱されたかどうかを調査することが必要です。
調査の結果、当該従業員のさぼり行為が軽微なものにとどまれば、懲戒権は行使できません。これに対し、職場離脱が長期間または頻繁に継続しており、貸与パソコンの前から離れる必要性もなかったのであれば、本人には、懲戒事由に該当する事実の存在につき合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の根拠と理由が認められるのであり、懲戒権を行使できることになります。
ただし、懲戒処分の重さが懲戒事由に照らして均衡を失してはならず、また、非違の程度が同じであれば、懲戒処分の内容も同種、同程度でなければなりません。これが否定されれば、いくら当該従業員の行為が懲戒処分を科す客観的・合理的な理由があったとしても、社会通念上相当とは認められないことになります。
当該従業員が外出していた時間は2時間ですから、必要以上に長いといえます。ただし、職場の秩序が乱されていないというのであれば、本当に懲戒処分を科すのが相当なのかどうかということが問題となり得ます。
当該従業員が離脱していた回数が少なく、本人のいうとおり次の商品企画が検討されており、業務に具体的な支障をきたしたことはないというのであれば、まずは今後同様の行為を繰り返すのであれば処分対象にすることを警告した上で、懲戒処分に至らない厳重注意をすることにとどめるということも考えられます。
懲戒処分前の措置にとどめたにもかかわらず、当該従業員がその後も所定労働時間中の離脱を続けるのであれば、厳重注意後の職務専念義務違反を含めて懲戒処分の対象とすることはやむを得ません。
その際でも当該従業員に弁明の機会を与えるなどの適正手続を怠らないようにしましょう。
執筆者プロフィール

弁護士・中小企業診断士 佐久間 大輔
榎本・藤本・安藤総合法律事務所
1993年中央大学法学部卒業。1997年東京弁護士会登録。2022年中小企業診断士登録。2024年榎本・藤本・安藤総合法律事務所参画。近年はメンタルヘルス対策やハラスメント対策など予防法務に注力している。日本産業保健法学会所属。
著書は『管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務』(日本法令)、『過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方』(労働開発研究会)など多数。
本記事が掲載されている特集:弁護士佐久間先生のコラム
記事
2025/06/16(月) コラム
2025/06/16(月) コラム
2024/07/01(月) コラム
2020/05/19(火) コラム
2020/05/19(火) コラム
2020/04/30(木) コラム
2020/04/24(金) コラム
2020/04/22(水) コラム
全15件(1〜10件を表示)