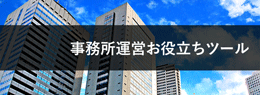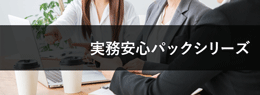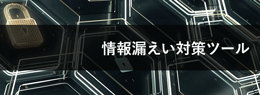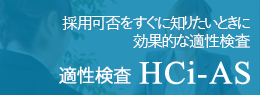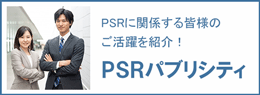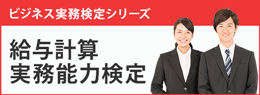中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査(令和7年9月)の結果を公表(日商)
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を取りまとめ、これを公表しました(令和7年9月9日公表)。
この調査は、令和5(2023)年10月に消費税インボイス制度が始まったことを受け、事業者の対応状況や負担の状況、各種負担軽減措置の効果等と、あわせて経理事務等のバックオフィス業務の状況等について調査したものです。
調査結果のポイントは次のとおりです。
〔インボイス制度〕
●インボイス制度導入前に免税事業者であった事業者のうち、BtoB中心事業者では78.6%、BtoC中心事業者では24.6%が、インボイス登録を実施。
●インボイス制度導入を機に、課税転換(インボイス登録)したことを契機に価格交渉を行った事業者は23.2%、うち76.9%が値上げを実現。
他方、価格交渉を行わなかった事業者は76.8%で、「受注先・販売先からの価格交渉の提案等がなかったから」が主な理由。
●課税転換(インボイス登録)した事業者の68.6%が「2割特例(納税額を売上税額の2割に軽減する措置。2026年9月末で終了予定)」を適用。
●インボイス制度導入後も免税事業者から仕入等を行う本則課税事業者は43.7%で、そのうち57.6%は仕入額が100万円以上。
●今後、免税事業者との取引価格や仕入先の見直しを行う本則課税事業者は42.3%。
他方、価格を維持したまま取引を継続する本則課税事業者は21.5%で、その理由としては「代替となる取引先がない」(44.6%)のほか、「地域貢献等の観点から小規模事業者を応援したい」(34.8%)といった回答も。
●制度導入により45.8%の事業者がコスト増を、73.4%の事業者が事務負担の増加を感じている。
〔バックオフィス業務〕
●「売上高1千万円以下の事業者」の約8割(79.4%)が1人で経理事務を行っている。
また、売上規模が小さくなるほど、専任の経理事務担当従業員がおらず、「売上高1千万円以下の事業者」の約8割(76.4%)が、代表者や営業担当者等が経理事務を兼務
●売上規模が小さくなるほど帳簿や試算表等の作成頻度が低く、また、各種経理業務システムの導入割合も低い。
規模が小さくなるほど、インボイス対応のためにツールを活用する割合が低く、また、経理業務のペーパーレス化が進んでいない。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」結果について>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/0909140000.html
※無断転載を禁じます
継続的な情報収集にはPSR会員登録がおすすめ!